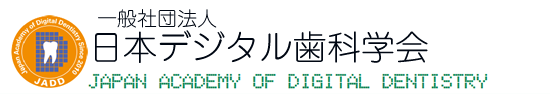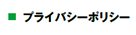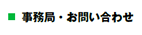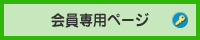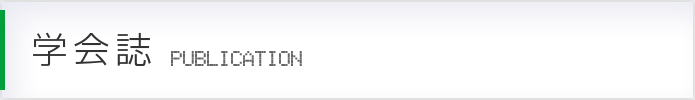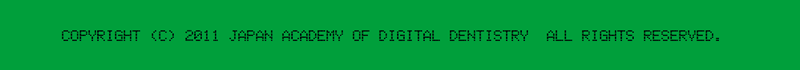- HOME
- 学会誌
学会誌
『日本デジタル歯科学会誌』『英文誌(Journal of Digital Dentistry)』は、J-STAGE上で論文を公開しております。下記よりご覧いただけます。
 |
|---|
論文の投稿について
投稿規定(253KB)
投稿票(27KB)
編集事務局
一般社団法人日本デジタル歯科学会
編集事務局
〒170-0003 東京都豊島区駒込1-43-9-501 一般財団法人 口腔保健協会内
TEL:03-3947-8301(代) FAX:03-3947-8073
E-mail:kikaku4@kokuhoken.or.jp
英文誌投稿論文について
一般社団法人日本デジタル歯科学会
会員各位
平素は、本学会雑誌へのご投稿にご協力を賜りまして誠にありがとうございます。
さて、これまで本学会誌にも英文論文をご投稿を賜ってまいりましたが、本格的な英文論文のご投稿を促進するために雑誌名も「Journal of Digital Dentistry」に改称し、会員の先生方はじめ、広く論文投稿を受け入れるように企画しています。
つきましては、2023年6月発行予定で英文誌を創刊することとなりました(年1回、毎巻2号)。
つきましては、英文誌投稿論文を2022年12月1日(木)から受け付けます。
なお、会員に限って創刊号の掲載料は無料とさせていただきますので、この機会にぜひご投稿いただけますようお願い申し上げます。
詳細は下記の英文誌投稿規定をご確認ください。
理事長 末瀬一彦
編集担当理事 金田 隆
研究倫理審査について
下記ページをご確認ください。
英文誌について
Journal of Digital Dentistry ISSN 2758-741X
Vol.1, No.1 (June 2023)-
英文誌に関しましては、会員専用ページにてご覧いただけます。
会員ID、パスワードをご用意の上、ご覧ください。
英文誌 Vol.3 No.1 June 2025
英文誌 Vol.2 No.1 June 2024
英文誌 Vol.1 No.1 June 2023
《Preface》On the publication of JADDʼs English Journal
The Japan Academy of Digital Dentistry is pleased to publish the English version of its Journal.
Since its establishment in 2010, the Academy has held regular academic conferences every year, attended by approximately 1,000 members.
Digitalization in dentistry has progressed rapidly, and in the past 12 years, there has been great progress, including advances in diagnostic imaging, the inclusion of CAD/CAM crowns in medical insurance, the evolution of zirconia materials with high color reproducibility, the high accuracy of intraoral scanners, and the shift to online medical receipts. The annual conference covers the latest topics and interesting studies, and awards for excellent studies are also given. The Japan Academy of Digital Dentistry is one of the world’s leading academic societies.
The Academy already publishes a journal in Japanese three times a year. With the start of the English version, in addition to disseminating Japan’s excellent research results globally, we will publish valuable original papers, clinical case reports, research studies, and other papers and reviews from overseas, thus increasing the value of our Academy.
In order to raise the usefulness of our English Journal, for the time being submission fees will be free of charge. We actively welcome submissions not only from Japan but also from overseas. For details, please refer to the Journal website.
The Japan Academy of Digital Dentistry
President Suese Kazuhiko
学会誌について
日本デジタル歯科学会誌 ISSN 2432-7654
Vol.4, No.1 (April 2014)-
日本歯科CAD/CAM学会誌 ISSN 2188-0069
Vol.1, No.1 (April 2011)-vol.3, no.1 (April 2013)
学会誌に関しましては、会員専用ページにてご覧いただけます。
会員ID、パスワードをご用意の上、ご覧ください。
学会誌 Vol.15 No.1 May 2025
第16回学術大会抄録集(10.8MB)
学会誌 Vol.14 No.3 February 2025
《巻頭言》まだ見ぬ世界への橋渡し
デジタル技術がもたらす変革は我々の想像を遙かに超えるスピードで生活空間に広がり,歯科分野でもCAD/CAM,デジタル印象など多岐にわたる技術が臨床現場に導入されています.
このような状況は私の学生時代(約40 年前)には夢物語でしかなく,私の指導教官であった故内山洋一先生(北海道大学名誉教授)が,1970 年代に補綴物の機械加工の必要性に関する論文を投稿したところ,ある高名な先生から「君は技術教育を軽視するのか!」とお叱りの電話があったそうです.ところが今やどうでしょうか.学生教育のレベルでもCAD/CAMの教育は必須であり,ついには学生実習で鋳造を行わずに歯科医師になる時代になりました.技術は常に進化し,移り変わるのです.
そして,今デジタルの世界で注目されているのは人工知能(AI)の開発です.近い将来,汎用人工知能(AGI)が開発され,人間の知能を超えるシンギュラリティーが予想されているのです.現在でもすでに限定した分野では人間の能力を超えているといえます.例えば,将棋やチェスなどのゲームでは人間はAI には勝てないことが常識であり,医療分野ではAI による画像解析は,レントゲン写真やCT などの画像から異常を検出する精度は人間を超えるとも報告されています.一方で問題となるのは,この技術をどのように取り入れ,コントロールしていくかです.最近,ニュースでAI が作成した学術論文が問題となっていることが報じられていましたが,AI の使い方によっては倫理的・社会的な問題となることもあります.AI の活用は人間の能力を著しく拡張し,日々の作業,意思決定,学習,創造活動を支援し非常に有益であることは明白であり,AI 使用の有無でのAI 格差は圧倒的な差となる可能性があります.そして今後AI の性能が加速度的に向上することを想定すると,我々はこの技術とどのように向き合うのか真剣に考える必要があります.
AI だけではなく,今後,歯科分野で新しいデジタル技術を応用するには,教育とトレーニング,研究開発,倫理規定とガイドラインの策定,技術の標準化,他分野との連携強化などが必要であり,これこそがまさに日本デジタル歯科学会が果たすべき役割です.そして,その積み重ねが次世代の歯科医療の実現につながるのであり,日本デジタル歯科学会の活動は今後の歯科分野のデジタル化を左右することになるでしょう.
会員の皆様のますますのご活躍に期待しています.
(一社)日本デジタル歯科学会
副理事長・学術委員長
疋田 一洋
学会誌 Vol.14 No.2 September 2024
《巻頭言》JADD のさらなる発展をめざして!
今年は,異常気象による酷暑,ゲリラ豪雨そして全国各地で地震などが発生し,自然災害に対する対策を真剣に考える年になっています.皆様の準備はいかがですか.
さて,5月に長崎で開催されました総会におきまして,再度理事長に就任させていただきました.会員諸氏のご協力のもと,これまで以上に精進し,本学会のさらなる発展に努めさせていただきます.ご指導,ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます.
本学会も2010年に東京都市センターホテルで設立総会を開催し,今年で15回目の総会・学術大会を開催することができました.コロナ禍にあっても,毎年定期的に総会・学術大会が開催できましたことは,大会長はじめ,スタッフならびに会員の先生方,賛助企業の皆様方のおかげであると感謝申し上げます.現在,本学会の会員数は1,000名,賛助企業は60社で,日本歯科医学会におきましても認定分科会の一員として,日本の歯科医療界におけるデジタルデンティストリーの推進役になってきています.
令和6年度の社会保険診療報酬改定におきましても「医療DX」「情報連携加算」「デジタル機器の導入」など,社会情勢を反映するかのように歯科医療界にもデジタル化の大きなうねりが来ています.本学会のミッションはますます大きく,歯科界発展,国民のために責任ある活動をしなければなりません.とりわけ口腔内スキャナーが保険診療に導入されたことは画期的なことであり,海外では自費診療に使用されている先進器機が,多くの国民に提供できる医療保険に収載されたことは斬新的なことです.これから,CAD/CAM冠や口腔内検査など適用範囲の拡大に期待しています.
このたび,日本歯科医学会の令和6年度のプロジェクト研究に申請していましたところ,「歯科医療におけるデジタル用語集の作成」が採択されました.昨年度の「歯科医療における匠の技のデジタル化―歯科技術の遠隔教育への挑戦―」に続いての快挙となります.歯科医療におけるデジタル化が急速に進展するなかで,歯科医学会として「用語」の統一化を図ることは極めて重要です.関連学会と協調して,「デジタル歯科用語集」の作成に努めていきたいと思います.
本学会も関連する多くの学会とコンタクトをとり,共催講演やシンポジウムなどを積極的に進めています.さらに,オープンアクセス可能な英文誌も発刊しています.海外からも積極的に投稿されることを促し,海外の情報を研鑽し,本学会の知名度を高め,世界をリードする日本デジタル歯科学会(JADD)に発展させたいと願っています.
会員の皆様のご協力をお願いするとともに,ご健勝を祈念します.
(一社)日本デジタル歯科学会
理事長 末瀬 一彦
学会誌 Vol.14 No.1 May 2024
第15回学術大会抄録集(40.6MB)
学会誌 Vol.13 No.3 February 2024
《巻頭言》歯科医療のDX化に向けたAI活用の取り組み
近年,仕事における働き方改革が浸透する中,コロナ禍を機に拡大する人材不足から,業務の効率化への問題がさらに深刻化している.その対策として経済産業省ではIT導入補助金を,厚生労働省では業務改善助成金を支給するとともに,企業や医院のDX(Digital Transformation,デジタルトランスフォーメーション)化の推進に注力している.
その中で現在注目されているのがICT(Information and Communications Technology,情報通信技術)とAI(Artificial Intelligence,人工知能)である.ICTとは,コンピューター,ネットワーク,データストレージ,ソフトウェア,インターネットなどのインフラに加えて,情報の収集・処理・通信に関わる広範な基盤である.AIはICTの基盤を活用することで,ビッグデータから機械学習や深層学習,自然言語処理などの手法を用いて,パターンや傾向を抽出し,問題を解決して予測を行い,システムやプロセスを最適化して,業務の効率化や自動化を実現する.
AIは人間のように自律的に意思決能力を持つ重要な中枢プログラムでもある.AIの進歩は非常に迅速で,研究者は新しいアイデアや技術の開発に注力しており,米国OpenAI社が開発した生成AIのChatGPTはまさに世界を変える革新的AI技術であり,大手ハイテク企業や大学など,さまざまな機関がAIの研究開発に莫大な資金を投資している.
歯科医療の中にもAIが活用され,診断・治療・予防などさまざまな領域で革新的な取り組みがなされている.以下に,AIが歯科医療において果たす役割について述べる.画像診断では,レントゲン,CTスキャン,オーラルスキャナーなどが機械学習アルゴリズムを用いて画像を解析し,むし歯・歯周病などの異常を検出し,疾患の早期発見早期治療が可能となっている.治療計画と治療法では,インプラント治療や矯正治療のデジタル化と最適化モデルの構築が可能となっている.患者とのコミュニケーションでは,チャットボットやオンラインプラットフォームにより,医院内の予約管理,自動電話応答,問診票による情報収集,診療後のリコールシステムなどが可能となっている.予防歯科医療では,患者の歯科履歴や他の医療機関情報から,将来的な疾患のリスク因子を予測し,適切な口腔ケア方法を指導するとともに,疾患の発症リスクを軽減させる予防策を提案することが可能となっている.特に日本の歯科医療では皆保険制度があるため,ビッグデータを収集してAIが解析しやすい環境が揃っている.
このように現在,歯科医療の中にAI技術は広く実用化され普及しており,個人向けのAI製品やサービスも市場に多く登場しており,多くの企業がAIを活用して業務の効率化やサービスの向上の取り組みを行っている.AIは医療に多大なる功績をあげているが,今後の課題としては,医療倫理的な問題や個人情報の保護,バイアスの排除,AIシステムの透明性など,規制の必要性も浮き彫りになってきている.
今後歯科医療のDX化推進のために,われわれ歯科医師が創造的なアイデアを駆使して,AIと上手く共存し,活用していくことが重要である.
5月に開催される日本デジタル歯科学会第15回学術大会(長崎大学生命医科学域口腔インプラント学分野 澤瀬 隆教授)でのテーマは,「AIによる歯科医療―ディープラーニングの活用―」であり,まさに現在のトピックの内容が目白押しである.
(一社)日本デジタル歯科学会
副理事長 水木 信之
学会誌 Vol.13 No.2 September 2023
《巻頭言》歯科界のデジタル化を牽引しましょう
ほとんど全ての学会がオンラインやハイブリッド開催を常態化し,各種の会議や委員会活動もリモートが当たり前のニューノーマルの時代に突入しました.誰もが予期しなかったこととはいえ,皮肉なことに新型コロナウイルスの感染拡大が世の中のデジタル化を加速させ,オフラインの行動を極端に制限させました.もしもデジタル技術がなければ,コロナ禍をどのように凌しのげたのか想像もできませんが,私たちは20 世紀後半からのデジタル革命を実体験しながら,仮想を超えて成長するデジタルトランスフォーメーション(DX)の多大な恩恵に預かり,効率的で多様性に富んだ日常を過ごすことができています.さらに今後もデジタルトレンドの情報収集に努め,AIやIoTを積極的に導入しながら,歯科医療を推進させていくことに多くの期待が寄せられています.
例えば,日本歯科医師会は2020年に発刊した「2040年を見据えた歯科ビジョン─令和における歯科医療の姿─」の中で,「歯科におけるICT活用の推進」や「医療データの標準化と生涯にわたる保存,PHRの活用の推進」などを掲げ,健康長寿の延伸に寄与するデジタル活用の必要性を明示しています.また,2021年に発表された日本歯科医学会の「2040年への歯科イノベーションロードマップ」においても,デジタル関連のアクションプランは多彩であり,第1期(2019~2025年)には「スマートフォンによる舌・口唇の検査が実用化」,「オンラインとオンサイトが創造するワンデートリートメント」,第2期(2026~2032年)には「ヴァーチャルリアリティー技術による遠隔支援システムが実用化」,「デジタル歯科医院の登場」,そして第3期(2033~2039年)には「AI診断により最適治療法が確立」,「AIロボットによる遠隔歯科支援システムが実用化」,「デジタル高次歯科病院の登場」などのマイルストーンを設定し,デジタル技術により画期的に変革する歯科界の将来像を予言しています.私自身も2040年まで何とか細々とでも現役の歯科医師を続けることができれば,デジタルデンティストリーの進化と並走して発展する歯科医療の体験者になれると胸躍らせている次第です.
(一社)日本デジタル歯科学会は,まさにこうした歯科界のデジタル化を真正面から主役として,力強く牽引する重要な役割を担っています.末瀬理事長の強力なリーダーシップの下で,関連する学会とも協力しながら,夢の実現に向けて確実に歩を進めなければなりません.私たちはデジタルリテラシーを高めながら,既に日常臨床に普及しつつあるIOSやCAD/CAMによるデジタルワークフローを定着,発展させ,巷でいわれているナショナルデータベース(NDB) をもとにAIを駆使した利活用を包含し,国民ひとり一人に最適な歯科治療を提供できるよう進歩し続けたいと思います.
(一社)日本デジタル歯科学会
副理事長 大久保 力廣
学会誌 Vol.13 No.1 April 2023
第14回学術大会抄録集(12.1MB)
学会誌 Vol.12 No.3 February 2023
《巻頭言》(一社)日本デジタル歯科学会に求められるもの
皆様,新たな気持ちで2023年を迎えられていると思います.今年は卯年,干支は「癸卯(みずのと・う)」です.「癸」には新たな生命が成長し始める状態の意味があります. 2023年は「癸」と「卯」の組み合わせですから,新型コロナウイルスの影響は相変わらずですが,これまでの努力が実を結び,勢いよく成長し飛躍するといった縁起の良い年になると期待しております.
本学会は、平成22年3月28日,設立総会となる第1回学術大会を東京で開催して以来,本年3月で13周年を迎えようとしております.設立以来,歴代理事長の強力なリーダーシップのもと,30名の理事,110名の代議委員,13の委員会を中心として学会活動を展開し,会員数も990名(令和5年1月現在)まで増えました.また,昨年4月1日に日本歯科医学会認定分科会として認められ,今後は専門分科会加入を目指すことになります.
さて,わが国でもデジタルトランスフォーメーション(DX),持続可能な開発目標(SDGs)といったキーワードがすっかり定着しましたが,こうした社会の動向と本学会を含めた歯科の活動は密接に関連しております.たとえば2022年6月7日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2022(骨太の方針)」には持続可能な社会保障制度の構築のために,歯科に期待される役割が以下のように明確に述べられています.
1.全身の健康と口腔の健康に関する科学的根拠の集積と国民への適切な情報提供
2.生涯を通じた歯科健診(いわゆる国民皆歯科健診)の具体的な検討
3.オーラルフレイル対策・疾病の重症化予防につながる歯科専門職による口腔健康管理の
充実,歯科医療職間・医科歯科連携を始めとする関係職種間・関係機関間の連携
4.歯科衛生士・歯科技工士の人材確保,歯科技工を含む歯科領域におけるICTの活用に
よる歯科保健医療提供体制の構築と強化
5.市場価格に左右されない歯科用材料の導入の推進
5.の「歯科用材料」についてのくだりは,金銀パラジウム合金価格の高騰に端を発していると考えられますが,本件についてはすでに末瀬理事長の発案で日本補綴歯科学会と共同でCAD/CAMクラウンの保険適応範囲拡大に向けた科学的根拠の取りまとめを行い,厚生労働省への情報提供を行っています.2.の「国民皆歯科健診」制度についても,本学会は積極的に関わっていく必要があります.この制度が実施されば国民の口腔健康状態についてのデータベース構築が急務です.その中に口腔内スキャナー・データが収載されれば,模型製作・保管に必要なコストや空間の心配なく口腔内形態の三次元情報を保存・共有・利用ことが可能となります.こうしたデータベースは治療の効率化に役立つばかりでなく災害時の身元確認にも活用できます.健診時の口腔内スキャニングは末瀬理事長が長年温められてきたアイデアです.また,ビックデータのAI解析により仮想空間での補綴装置の自動デザイン,インプラント・矯正治療の自動プランニング・システムといった,近未来の歯科医療実現にも繋がります.行政の動きを待って対応するのではなく,学会の英知を結集して夢のある未来像を具体的に描き,行政を後押しするような活動が求められていると思います.皆様の引き続きのご支援を宜しくお願いいたします.
(一社)日本デジタル歯科学会
副理事長 馬場一美
学会誌 Vol.12 No.2 September 2022
《巻頭言》(一社)日本デジタル歯科学会のさらなる発展をめざして
今夏も異常気象の暑さに見舞われ,新型コロナウイルスの感染対策と共に日常生活にも支障をきたしていますが,会員の皆様方におかれましてはいかがお過ごしでしょうか.
平素は,本学会の運営にご支援,ご協力を賜りまして心より厚く御礼申し上げます.
さて,本年6月の総会におきまして,理事長の再任をご承認いただきまして誠にありがとうございます.代議員会でお認めをいただきました役員の先生方とともに責任をもって本学会のナビゲートをさせていただきます.
2010年に『日本歯科CAD/CAM 学会』として設立させていただきました本学会も2014年には「日本デジタル歯科学会」に改称し,一般社団法人格を取得させていただきました.12年経過しました現在では,会員数も950名に達し,協賛企業も58社に上っています.さらに,本年4月1日からは日本の歯科医学会の総本山でもある日本歯科医学会認定分科会の一員に加盟させていただき,光栄であるとともにその責務の重さをひしひしと感じています.
国政においてもデジタル化が推進される社会にあって,歯科医療を担う本学会の役割はきわめて重要であり,常にリーダーシップをとらなければなりません.歯科診療においても「CAD/CAM冠」「口腔内スキャナー」「ジルコニア」「画像診断」「オンライン請求」など,急速にデジタル技術が導入され,国民の口腔の健康を維持増進していくうえで,「安全,安心,効率的」な歯科医療の提供体制を支えていかなければなりません.
これまでの学会運営の経緯を鑑み,従来からの常置委員会のさらなる活性化と共に,今期から新たに「教育問題委員会」「医療保険検討委員会」を設置し,さらに「専門医・技術認定士制度委員会」「専門医・技術認定士認定委員会」に統合し,より機能的な組織運営を図っていきます.歯科医療においてデジタル化の普及が急速に進展し,大学や専門学校における教育面が追随していない状況を踏まえ,「教育問題委員会」において,デジタル歯科医療の指導内容の在り方について提言し,さらに「医療保険検討委員会」では医療保険における新たな器材や技術の導入を図るべく技術提案書の作成なども積極的に行ってまいりたいと考えています.また,「専門医制度」について議論が行われている昨今にあって,本学会では「歯科医療の基本は技術力」であることを再認識する上で,専門医ならびに技術認定士の資格試験に実技試験を導入すると共に,本学会の特徴を活かすべくAIを取り入れた筆記試験も行っています.今後さらに学会誌の価値を高めると共に,海外からの論文投稿も可能にするための英文雑誌の刊行も視野に入れています.
日々刻々と変化,進展する「デジタルデンティストリー」を支援し,歯科医療界に広く啓蒙するために,関連他学会とも協調を図り,国民の健康長寿に少しでも貢献できる学会に軌道を整えていきたいと考えています.会員諸兄におかれましては,今後ともなお一層のご支援,ご協力を賜りますよう衷心よりお願い申し上げます.
(一社)日本デジタル歯科学会
理事長 末瀬一彦
学会誌 Vol.12 No.1 April 2022
第13回学術大会抄録集(19MB)
学会誌 Vol.11 No.3 February 2022
《巻頭言》歯科界のさらなる進展を目指して~デジタルと人の心で繋ぐ襷~
私は歯科技工専門学生時代にピンレッジの製作方法を教わった世代である.程なくしてロストワックス法が主流になり,アメリカにおいて桑田正博先生らのチームにより開発された陶材焼付鋳造冠が,国内で急速に普及していく様を目の当たりにした.時代の大きな移り変わりを感じたものである.その後も歯科界の進展は連綿と続き,現在,私たちはデジタルデンティストリーのさなかにいる.
私がデジタルに興味を持ったきっかけは,パーソナルコンピュータが急速に発達した頃である.「歯科技工業界にはどのようにデジタル化が訪れるのであろうか?」と気にとめていた.なぜならば,ヒトの口腔内は,髪の毛1本,砂一粒でも感知できるほどに繊細であるがゆえに,歯科技工は一般工業界のような機械加工の参入は難しく,熟練の技のみによって支えられるものだと考えていたためである.
転機は2005年に訪れた.当時国内で唯一ジルコニア加工が可能な初代CAD/CAMシステムを導入する機会を得,インストラクターを仰せつかったのは幸運なことであった.当初はジルコニアを削る手段として,鋳造がミリングに置き換わったという感覚でしかなく,この新しい手法を臨床応用するために楽しんで追求した日々であった.
次第にデジタル技術は技工物製作の枠組みのみならず,歯科医療全体に大きなうねりとなって革新をもたらし始めた.多くの情報が溢れ,一体どの情報を取り入れたらいいのか迷い埋もれそうになりながらも,変化すべき点は素早く取り入れ,変化してはならぬことは変えず,保ちながら行動することを心がけるようになった.
デジタル技術は便利である.当技工所で毎朝拠点間を繋ぎ全員朝礼を行うことができているのもデジタルのおかげである.皆さんもミーティングや学会等でオンライン参集する機会が増えたことと思われる.便利になった一方で,画面越しの相手の「気」「元気」「勇気」,画面に映らない周りの「雰囲気」を感じることは難しいのではないだろうか.また,相手の気持ちを推し量ったり,自分の気持ちを正確に伝えたりすることが難しい時もある.この点に早く気づいて対処していかないと,これまで日本人が大切にしてきた「お互いを思いやる気持ち」「相手の立場に立つ気持ち」を見失ってしまうかもしれない.
現在国が推進しているのは,デジタル活用により人々の生活をより良い方向へと変革し,既存の価値観を根底から覆す斬新的なイノベーションである.今後歯科界においても,多くの情報がAI処理できるようになり,指数関数的な変革がもたらされる可能性を秘めている.そのような時代にあって,最先端を担うこのデジタル歯科学会で,自分の実力以上の役職と挑戦の機会をいただいていることに感謝しながら,組織運営のお役に立ちたいと考えている.会員の皆様とともに,「デジタル」と「人の心」で日本の歯科医療のさらなる発展を目指し次世代へと襷を繋ぎたいと願っている.
(一社)日本デジタル歯科学会
副理事長 木村健二
学会誌 Vol.11 No.2 September 2021
《巻頭言》革新的デジタルイノベーションによる次世代への展望
2021年夏,東京オリンピック・パラリンピックが無観客の静寂の中で華やかに開催された.その裏では一向に終息の兆しが見えないコロナ変異株の感染拡大から,幾度となく緊急事態宣言が発令されたが,それでも感染者数は日々過去最多を更新し続けている.医療現場ではワクチンの供給が滞り,重症化のリスクも高まり医療崩壊も危惧されている.世はまさに新型コロナウイルスの脅威に翻弄されており,その変化の中で人は新しい価値観の生活様式を余儀なくされ,在宅テレワーク,オンライン会議,ネット社会でのデジタライゼーションが加速している.
こうした社会背景に伴い,国ではデジタル社会の実現に向けたデジタル改革関連法案が制定され,内閣府にデジタル庁が設置された.ネットワークと流通環境の整備,行政や公共分野におけるサービスの質の向上,人材の育成と教育・学習の振興など,一人ひとりのニーズに合った多様な幸せを実現するデジタル社会の構築である.
近年産業界では第4次産業革命がクローズアップされ,その中心はAI(Artifical Intelligence;人工知能)とIoT(Internet of Things;モノのインターネット)である.通信業界では5Gの通信網が配備され,超高速・超低遅延・超大量接続が可能となり,AIによるビッグデータの解析,IoTによりあらゆるモノがネットワークで繋がることで,技術革新と生産性の向上がなされている.
これらAIとIoTを駆使した次世代産業としては,自動運転車(テスラ),バーチャルリアルティ(仮想現実VR・拡張現実AR・複合現実MR),ウェアラブルデバイス(スマートグラス・アップルウオッチ),ドローン(物流・交通手段),ロボット(ナビゲーション・ダビンチ手術),フィンテック(電子マネー,キャッシュレス決済)などが開拓されている.トヨタが創る近未来都市「ウーブン・シティ」は,自動運転車・ロボット・住宅など,モノや人がインターネットで繋がり(IoT),集めたビッグデータを人工知能(AI)が活用する先端技術を駆使した街創り構想である.
歯科医療界のデジタルデンティストリーにおいては,インプラント治療に代表されるように,コンビームCT画像(DICOM)と口腔内スキャナー(STL)とフェイシャルスキャナーによる3次元の検査・診断,各種ソフトウエアによる3D解析とシミュレーション,ナビゲーションおよびガイデッドサージェリー,CAD/CAMと3Dプリンターによるデジタル補綴修復の一連の流れが構築されている.また歯科医院内における患者説明用デジタルツールや,患者情報のデジタルデータベース化とクラウドを介した一元管理,遠隔医療やオンライン診療なども臨床応用されている.
本学会のデジタルを活用した特殊性・独自性においては,今後,日本歯科医学会への加入と共に産学官連携の推進を目指している.大学・研究機関による研究の成果,民間企業による技術の活用とオープン化,行政による保険診療導入の実用化等,産学官の共創による次世代への展望が期待される.
(一社)日本デジタル歯科学会
副理事長 水木信之
学会誌 Vol.11 No.1 April 2021
第12回学術大会抄録集(10MB)
学会誌 Vol.10 No.3 February 2021
《巻頭言》歯科のデジタライゼーションを加速しましょう
今年9月に日本の行政機関として「デジタル庁」が新設されます.菅内閣の看板政策として,国や地方全体のIT化やデジタル・トランスフォーメーションの実現,推進を目指すものです.世はまさにデジタライゼーションの急加速に向けてアクセルペダルを強く踏み込んでおり,歯科におけるデジタル化も必然的潮流といえるかもしれません.
私ごとになりますが,大学院生時代から補綴装置の精度や強度といったものに深い関心がありました.特に義歯設計やフレームワークの構造設計が大好きで興味を持ち続けてきました.自身の臨床でデジタル技術を導入するようになったのは特段早いわけではなく,15~16年前にインプラントのガイデッドサージェリーや上部構造フレームワームのCAD/CAM製作からです.それまでのフリーハンド埋入から,サージカルガイドの利用で正確な埋入位置や方向を規定できることを確認したときには大きな驚きがありました.上部構造の製作に関しても,フルマウスのインプラント支台ワンピースフレームワークがパッシブフィットした時の感動を今でも覚えています.
特にデジタル技術にのめり込むようになったのは,専門とする有床義歯製作にCAD/CAMが応用されるようになってからです.材料学的には大きな発展があったにせよ,長年ほとんど変化のなかった義歯の製作術式がCAD/CAMを応用することにより劇的に変化することが予想されます.不可避とされていた金属の鋳造収縮やレジンの重合変形がなくなることは,歯科技工士や歯科医師の悲願であったはずであり,設備や費用の点を除けば義歯製作の軍配はデジタル側に上がることは確実です.IOSにより記録された口腔内の形状データからCAD/CAMにより高精度,高強度な義歯が完成できる日が近づいていることを実感しています.さらにはデジタルデータを記録,保存することにより,その後の再製作や修理にも大幅に役立つはずであり,近未来の義歯の臨床術式に画期的な変革が訪れると思われます.
本学会はこうした近未来を確かなものにするために,デジタルの基礎研究や臨床を力強く推進するとともに,デジタル歯科専門医や専門士を養成し,適切な制度に基づいて認定していくことになります.その結果,本会が自信を持って認定した専門医や専門士の方々が製作,装着する補綴装置が欠損で悩む患者の健康寿命の延伸に大きく貢献すると期待しています.
1日も早くそうした日が実現されるために,本学会は総力をあげてデジタル歯科治療の推進に向けた教育,臨床,研究を支援するとともに,専門医,専門士制度の制定と普及に努めていきたいと思っています.副理事長として大変力不足ではありますが,精一杯尽力する所存でございますので,会員の皆様方のご指導,ご鞭撻をどうぞよろしくお願い申し上げます.
(一社)日本デジタル歯科学会
副理事長 大久保力廣
学会誌 Vol.10 No.2 September 2020
《巻頭言》理事長就任にあたって
今年は,「コロナ禍」「異常気象」と例年になく国民の日常生活を脅かす年になっていますが,被災されました方々には心よりお見舞い申し上げます.
会員の皆様方におかれましては,いかがお過ごしでしょうか?
さて,6月の総会および理事会におきまして本学会の理事長として再任していただきました.微力ながら,会員の皆様方の温かいご支援,ご協力を得て,これまでの経験,反省を活かしながら職務に精一杯務めさせていただきたいと存じます.何卒よろしくお願い申し上げます.
「コロナ禍」の蔓延により,日常生活をはじめ診療体系や学会開催の変更が余儀なくされ,各方面の仕事や学校教育,学会開催の「デジタルシステム」によるテレワーク,オンライン化が注目されています.これからは,元の状態に戻ることはなく,「新しい生活様式」「新しい学会のあり方」などを検討していかなければなりません.まさに,本学会の真価が問われるところであり,本学会もトップリーダーとしての役割を果していかなければなりません.会員の皆様方の奇抜なアイデアに期待しています.
2010年に設立した本学会も10年を経過し,黎明期から成熟期に入ってまいります.「会員増強」「専門医・専門士資格の充実」「デジタル機器の普及」「学会誌のさらなる充実」「日本歯科医学会への加盟」などなど,まだまだ多くの課題があります.保険診療においてもデジタル機器を用いた検査や診療項目が徐々に拡大され,国民の歯科医療が高品質で,効率的に,快適に行われるようになってきています.本学会においても関連学会と協調しながら,行政への提言もしていきたいと思います.任期中には会員数が1,000名に達するように各方面に本学会の存在価値をアピールしたいと思いますが,そのためには「臨産学」が一体となって魅力のある学術大会やセミナーの開催,学会誌の発信などを行う必要があります.
「一人では何もできない.しかし,誰かがやらなければ何も始まらない!」の精神をもって,「一意専心」理事長を務めさせていただきたいと存じます.会員の皆様方には,これまで以上のご厚情,ご協力を賜りますよう衷心より深くお願い申し上げます.
まだまだ,厳しい社会情勢が続きますが,皆様方におかれましてはくれぐれも御身御自愛頂き,お健やかにお過ごしください.
(一社)日本デジタル歯科学会
理事長 末瀬一彦
学会誌 Vol.10 No.1 April 2020
第11回学術大会抄録集(10MB)
学会誌 Vol.9 No.3 February 2020
《巻頭言》(一社)日本デジタル歯科学会の包括的アウトカム活動を目指して
わが国の政策(国家戦略)として,これからの未来を見据えた社会像「Society 5.0」を目指しています.すなわち,狩猟社会(Society 1.0)から始まった文明を農耕社会(Society 2.0),工業社会(Society 3.0),情報社会(Society 4.0),そしてこれからはサイバー空間と現実世界を高度に癒合させたシステムにより,経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会(Society 5.0)とされています.このようにみると,まさに現在は情報社会環境に包まれているといえます.情報の伝達方法をふり返れば,身振り・手振りなどから始まり,絵や文字,音や狼煙,飛脚・郵便,通信・電話・無線電話,そしてデジタル情報によりインターネットが登場し,現在では地球上はもとより宇宙空間とも情報伝達は可能となり劇的に変化してきました.
一方,歯科分野の修復装置製作手法としては,金属加工では圧延・板金加工から始まり鋳造,切削法,有機材料では塡入・築盛,切削法などが行われてきました.デジタル情報に関しては今世紀初頭から切削法によるCAD/CAM 法が取り入れられ,アルミナスポーセレンなど一部セラミックスの切削加工が可能となりましたが,最近では加工が困難とされていたジルコニア素材の加工も可能となり臨床応用されてきています.また,加工法も切削のみではなく積層法も応用され,切削法では限界とされている微細な形態再現も可能となり,デジタル情報の活用が大いに期待されているところです.
歯科におけるデジタル情報の伝達に関しても,診断・設計から始まり印象採得,修復装置の製作,装着後の確認など一連の作業がパラレルに連携が図れることも大きな利点であります.例えば,CT,X 線等の情報からインプラント埋入,上部構造製作までの一連の工程での活用が可能となってきています.しかも,その情報は局地ではなく遠隔地での活用も可能であり,医科分野ではすでに実践されております.
このように,現在ではデジタル情報をいかに取り扱い,連携させ,包括的に歯科医療に貢献できるかが問われているかと思います.その意味では,歯科分野でデジタルを対象とした学会としての役割,情報発信は重責で歯科医療専門分野での包括的な活動が期待されるところであります.
しかし,ヒトを対象とした歯科医療の分野としては,デジタルの1と2の情報のみではなく,その間のアナログ情報も必要で,両者の協調・癒合が必要と考えます.これらの結実を社会に活かすことにより,冒頭の「Society 5.0(人間中心の社会)」にマッチングし貢献できるアウトカム(Outcome)を可能とする学会といえるかと思います.
その意味でも,会員の皆様方におかれましては包括的で将来性ある本学会への積極的な参画をお願い申し上げます.
第11回学術大会は,「デジタル歯科力の進化─現在そして未来─」をメインテーマに2020年4月25日(土)~26日(日)愛知県名古屋市の「ウインクあいち」にて武部純大会長のもと開催されます.会員諸氏の学習・研鑽の場としてご活用頂ければ幸いです.
(一社)日本デジタル歯科学会
副理事長 齊木好太郎
学会誌 Vol.9 No.2 September 2019
第10回学術大会抄録集(11.5MB)
学会誌 Vol.9 No.1 August 2019
《巻頭言》デジタルデンティストリーにおける日本デジタル歯科学会の役目
2019年3月12~16日,ドイツのケルンで第38回International Dental Show(IDS2019)が開催され,166カ国から約16万人の人々が参加し,出展企業は 64カ国 2,327社に及んだ.このIDSは世界最大のデンタルショーで,2年間隔で開催される.
今回の特徴は,展示会場すべてがデジタルに関連した機器類,材料といっても過言ではない.わずか 5 年ほど前には CAD/CAM機器の展示が主流であったが,今回は既に限られた機種に淘汰され,口腔内スキャナー,チェアーサイドでのミリング,3Dプリンターが脚光を浴びていた.それに伴い使用される材料も CAD/CAM機器で使用する材料が主体となり,従来展示されていた金属類,印象材料などの展示はほぼ見当たらなかった.
米国の雑誌での報告によれば,2018年度のクラウンブリッジの83%がミリングによって製作され,8年前の20%から製作方法が著しく変化している.また,ジルコニア材料の100%がミリングによって製作され,PMMAで89%,e.maxなどの二ケイ酸リチウムガラスは 44%,WAXによる原型も80%はミリングで製作されていると報告されている.
口腔内スキャナーの普及も著しく,米国の歯科医師の60%ほどが使用し,単冠などの症例であれば,模型製作をすることもなく,診療室,あるいは歯科技工所で補綴物が製作される時代になりつつある.そして,診療所内での患者の口腔内スキャニング,補綴材料のミリング,補綴物完成は患者へのチェアータイムの減少につながり,患者の満足度に貢献している.
これからの時代を考えると,世界的なデジタル化はさらに急速に進むことが予想され,歯科医療従事者も歯科デジタルの勉強に取り組むことは必須事項である.
日本デジタル歯科学会は 2010年に世界で最も早く設立されたデジタル学会であり,一般社団法人化も行われ,大学,臨床家,企業が一体となった学会である.学術大会においても特別講演,基調講演,企業講演,ポスター発表など内容も充実している.また,著しく変化する歯科事情に合わせて開催される春季 , 夏季,冬季の研修会は好評を博し,常に定員に対して満席の盛況である.最近では,米国,ヨーロッパ,中国など海外諸国と連携を取り,国際大会を開催する時代となりつつある.
今年の10月4日(金)~6日(日)は第10回学術大会と共に第5回国際デジタル歯科学会が奈良春日野国際フォーラム甍で共催される.「温故知新 いにしえの都で最新のデジタルデンティストリーを語ろう!」のテーマのもとに,著名な演者の講演,最新機器の解説などが行われる.詳しい参加登録などは大会公式ホームページをご覧ください.多くの方々のご参加を期待しております.
(一社)日本デジタル歯科学会
副理事長 坂 清子
学会誌 Vol.8 No.3 February 2019
《巻頭言》デジタルデンティストリーのイノベーション
歯科の治療の歴史は古く,紀元前の遺跡から発掘された人骨にすでに歯の治療の跡が認められています.地中海でフェニキア人が盛んに交易を行っていた時代のシドンという町(現在のレバノンのサイダ市)では,下顎中切歯,側切歯の2本が欠損した部位に象牙を彫刻した人工歯を他の前歯に金のワイヤーで固定した人骨が発掘されており,またイタリア半島中部で栄えたエトルリアでは抜けた上顎中切歯を金の板で隣在歯に固定して治療した人骨が発見されています.
現代においては,クラウンブリッジ補綴領域では,昭和30年代にそれまで行われていた咬合面圧印帯環金属冠(Morrison Crown)から全部鋳造冠へと一大変革が起きました.鋳造冠はそれまで行われていた帯環金属冠に比べて適合が良く,強度も強いため,今日までクラウンブリッジのゴールドスタンダードとして広く用いられてきました.しかしながら,鋳造冠では一度金属を溶かして流し込み固めるために,結晶の偏析が起きたり,鋳造欠陥が生じたりすることにより,材料が持つ優れた性質を 100%生かすことができませんでした.
デジタル化の波が歯科にも押し寄せ,機械加工でブロックを削り出し,クラウンブリッジを作製することにより,もともとの材料が持つ優れた性質を 100%受け継いだ補綴装置を作ることができるようになり,昭和 30年代に帯環金属冠から全部鋳造冠へと一大変革が起きたと同じように,鋳造冠から CAD/CAM冠へと今まさに第二の大変革期を迎えております.
2005年に CAD/CAMを用いたジルコニア修復が厚生労働省の薬事承認を取得し,今まで不可能といわれていた臼歯部ロングスパンブリッジを含め,ほぼすべてのクラウンブリッジの治療がメタルフリーで行えるようになりました.
歯科におけるデジタル化はここにきて驚異的なスピードで進んでおり,光学印象装置,バーチャル咬合器や 3Dプリンターなども開発されるなど治療計画から補綴装置の作製までトータルで幅広く臨床応用されるようになってきました.
一般社団法人 日本デジタル歯科学会では,国民が最新の安全な歯科治療を安心して受けられるようにデジタル技術の歯科へのさらなる導入,発展に向けて学会誌の発行,セミナー,シンポジウム等の開催,学術大会の開催を行っております.
第10回学術大会は,2019年10月4日(金)~ 6日(日)まで本学会理事長の末瀬一彦先生が大会長で「温故知新 いにしえの都で最新のデジタルデンティストリーを語ろう!」をテーマに,「奈良春日野国際フォーラム 甍~I・RA・KA~」で開催されます.同時に第5回国際デジタル歯科学会(5th Annual Meeting of the International Academy for Digital Dental Medicine)も併催されます.詳細は学会HPをご覧ください.
今,社会はデジタル技術なくしては過ごせない世の中になっております.今後とも会員諸氏のご支援,ご協力,ご教示を賜りますよう何卒よろしくお願い致します.
(一社)日本デジタル歯科学会
副理事長 三浦宏之
学会誌 Vol.8 No.2 September 2018
《巻頭言》理事長就任にあたって
平成30年度の学会役員会ならびに総会におきまして,理事長に再任いただきました.まだまだ浅学菲才ではございますが,選任されましたからには持てる力を精一杯発揮し,学会の発展のために務めさせていただきます.
本学会は2010年に「日本CAD/CAM歯科学会」として発足し,東京(4回),大阪,福岡,札幌,横浜,盛岡と9回の学術大会を開催してまいりました.学会開催ごとに会員数も増加し,現在700名に達し,学会を根底からご支援いただいている賛助企業も50社に及びます.まだまだ未熟な学会ですが,日本のデジタルデンティストリーのリーダーとして会員の英知を結集して精進したいと思います.
さて,今期の執行部は役員に新戦力を加え,委員会活動を活性化させたいと考えています.
・総務・財務委員会:会務の総括と財政基盤の確立
・学術委員会: 第10回および第11回学術大会,第5回国際学会の企画,準備,夏季・冬季セミナーの企画運営
・編集委員会: 学会誌の年3巻の編纂・発刊,投稿規程の見直し,学会誌の充実,学会誌のデジタル化,投稿促進
・国際渉外委員会:第5回国際学会(IADDM)の企画運営,近隣諸国との交流の活性化
・国内渉外委員会:関連学会との積極的な協調,共催講演会の開催,会員増強
・専門医制度委員会:学会専門医の認証,試験方法,称号の検討
・専門士制度委員会:学会専門士の認証,試験方法,称号の検討
・顕彰委員会:各種表彰規程の作成,表彰の選考準備
・広報委員会:学術大会やセミナーの告知,会員増強の施策,関連企業の勧誘
・倫理委員会:学会発表に伴う倫理規定の整備,情報管理
上記委員会委員長には,経験豊富な理事の先生方にお願いし,委員には代議員を中心にご推薦いただきました.今後も必要に応じて委員の拡大を諮っていく予定です.なお,役員リストは次頁以降の「役員一覧」,「委員会委員一覧」をご確認下さい.
また,理事長諮問委員会として下記の3つの委員会を立ち上げる予定です.
・国際学会準備委員会:5th IADDM 開催の準備,企画,運営(他の委員会と協調)
・調査研究委員会: デジタル化の普及を目指して,臨床現場における CAD/CAM システムおよび口腔内スキャナーの現状把握調査
・教育内容検討委員会: 教育機関におけるCAD/CAMシステム導入および教育内容に関する現状把握調査,デジタルデンティストリーに関するコアカリキュラムの作成
日本のデジタルデンティストリーは諸外国に比べて普及途上にあります.画像診断では CBCT が臨床現場でも診断のツールとして有用に活用されていますが,医療保険における電子カルテは医科に比べてもまだまだ低い普及率です.保存修復や補綴領域における CAD/CAM システムは歯科技工所で約60%,歯科医院では10%に満たない導入率です.さらに,教育分野においては歯科医師国家試験にすでに口腔内スキャナーに関して出題されているにも関わらず,各大学における教育内容にはかなりの温度差があるようです.本学会が中心となり,日本のデジタルデンティストリーの実態把握をするとともに,普及促進活動をしていかなければなりません.
2014年から医療保険にも CAD/CAM 冠が導入され,小臼歯から大臼歯へとメタル修復に変わる新素材として期待されています.また,ジルコニアも透光性が高まり,モノリシックジルコニアとして高い審美性が得られます.日本の企業の英知の結集によって新素材の革新には目覚しいものがありますが,機器に関する開発が遅れているようです.近い将来,患者に優しい口腔スキャナーによる光学印象,3Dプリンターを中心とした付加造形装置の活用が期待されています.
本学会ではこれからも臨床現場の歯科医師,歯科技工士,歯科衛生士,新しい領域の開発に携わる研究者,日本の良質な材料・器械を開発し,普及させる企業関係者が三位一体となって,国民に安全,安心,信頼できる歯科医療を提供できるよう研鑽に努めたいと考えております.
会員はじめ,皆様方のご支援,ご協力,ご教示を賜りますようお願い申し上げます.
(一社)日本デジタル歯科学会
理事長 末瀬一彦
学会誌 Vol.8 No.1 April 2018
第9回学術大会抄録集(5.6MB)
学会誌 Vol.7 No.2 December 2017
《巻頭言》デジタル化の歯科学会フロントランナーとして
(一社)日本デジタル歯科学会は,2010(平成22)年3月28日に「日本歯科CAD/CAM 学会」として会員数200名強の学会としてスタートしました.
その後,2013(平成25)年4月に「日本デジタル歯科学会(Japan Academy of Digital Dentistry)」(以下,本学会)と改名して,2016(平成28)年には一般社団法人化し現在678名の会員,49社の賛助会員により構成・運営されております.
社会でのITあるいはIoTと称される技術革新・進歩は想像以上のスピードで進展しております.本学会発足当時の歯科界でのデジタル化は,歯科技工分野での加工法であるCAD/CAM が主でありましたが,今では,歯科診療・治療,診断分野も含めて広範囲にデジタルソリューションとして活用可能となってきています.そのような現状・将来性を鑑み改名に至りました.
野村総合研究所とオックスフォード大学の共同研究によれば,約20年後の社会における労働人口の約49%は,デジタル化(人工知能やロボット等の活用)によりその労働力の補完可能との発表がありました.
一方では,創造性や社会との協調性が必要な業務や非定型的で微細な業務は,将来においても人が担うともいわれています.
このように,今後の歯科界においてもデジタル化はますます進展すると考えられます.とりわけ,歯科修復装置の製作にとどまらず,口腔内スキャナー,診断器機,設計ソフト,顎運動測定・再現器機,模型製作,3Dプリンター,また,切削と積層によるハイブリッド複合加工機などの活用が驚異的な早さで現実化し臨床にも応用されるようになってきております.しかも,それぞれの連携が必要なところはそれが確実となり,また,遠隔操作による作業も可能になるかと思います.
一方,日常の歯科臨床では,対象としているのが個々の患者様でありおのずとその個々に適したカスタムメイドの作業,例えば,よりその患者様の顎機能に調和した咬合面形態や個性的な色調(彩)・形態再現などの微細な作業や個性化も必要となります.そのためには,過去に習得した知識と技術による熟達した手作業が不可欠でしょう.なおかつ,デジタルとの連携がスムーズに行われなければなりません.
このような背景をふまえ,本学会として歯科医療に関わる多くのデジタル機器や材料の開発,技術の研鑽,啓蒙などを活発に行い,国民に安全で安心して信頼頂ける歯科医療の提供を目的としたエビデンスの構築をしたいと考えております.
そのための活動として,学術大会の開催,学会誌発行,セミナー・シンポジウム等の開催を行っており,本号より学会誌においては学会HP からのオンラインジャーナルとさせて頂きました.
今後ますますデジタル化が進む社会に対応できる学会を目指してまいりますので,会員諸氏のご理解とご協力を何卒よろしくお願い致します.
(一社)日本デジタル歯科学会
副理事長 齊木好太郎
学会誌 Vol.7 No.1 April 2017
《巻頭言》デジタルデンティストリーの普及と今後
2017年3月21日から25日まで,ドイツのケルンで第37回International Dental Show(IDS2017)が開催され,157カ国から約15万人の人々が参加し,出展企業は59カ国2,305企業に及んだ.
このIDSは2年間隔で開催されるが,使用されるビルディング数は回数を重ねる毎に多くなり,展示スペースも拡大している.そして,1つのビルディングはまるでCAD/CAM機器のみの展示と言っても過言でないほどデジタル化の波が押し寄せてきている.この約20年間で見ると,先進国を中心に徐々に進んできたデジタル化も最近では,急激に普及し,発展途上国でも普及しつつある.その理由は,デジタル機器の小型化に伴い購入価格が安くなり,規模の比較的小さい歯科技工所でも容易に購入できるようになった事,機器が簡略化されて初心者にも操作しやすくなったことから,特別の機器という感覚がなくなった事などが挙げられる.又,従来はチェアサイドより技工サイドでのCAD/CAM応用が中心であったが,最近ではチェアサイドに於けるデジタル化が 急激に進み,IDSでも,口腔内スキャナー,チェアサイドミリングなどの展示が増えてきた.
この展示会を見ていると近い将来の動向が掴めるが,歯科全体がデジタル化に向かいつつある事を予想させる.勿論,全ての分野がデジタル化で解決するわけではなく,機器を使用してスムーズに出来る分野は機械化で,人にしかできない分野は今迄の習得した技術,能力を発揮していく時代になりつつある.こうした歯科界の方向性を見るにつけ,歯科医師はじめ歯科衛生士,歯科技工士においても,デジタル機器についての勉強は必須項目となり,常に新開発されるデジタル機器の動向に注力しなければならない.
日常臨床の中でデジタル機器を上手に使いこなしていくことは,患者さんのチェアータイムの減少に繋がるメリットがある.又,技工分野においても,従来は技術者の熟練度によって修復物の品質の良否が大きく左右される事が多々あったが,デジタル化によりその差が減少し,修復物の品質の安定化につながりやすい.機械化が進めば,技術の差が少なくなることは良いことであるが,機械化以外の所でどのような特徴,技術の差を出していくかの真価を問われる時代が訪れるであろう.
技工においては,機械化により比較的安定化した補綴物が製作される一方で,究極の高品質の補綴物を望む患者も必ず存在するので,この要求に応える分野と二分化していくものと思われる.又,チェアーサイドに於いては,患者さんにとって如何に負担が少ない治療をするかにデジタル化は大いに関係する時代となるであろうし,それに合わせて患者さんとのコミュニケーションの取り方の良否が今まで以上に重要な時代になると推察出来る.
一般社団法人日本デジタル歯科学会
坂 清子
学会誌 Vol.6 No.1 May 2016
一般社団法人日本デジタル歯科学会の設立について
学会会員の皆さん,お元気ですか.
平素は本学会会務運営にあたりご尽力をご尽力を賜りまして誠にありがとうございます.
本学会も「日本歯科CAD/CAM学会」として,平成22年3月28日に東京 都市センターホテルにおいて「設立記念学術大会」を開催し,最初の一歩を踏み出しました.以来,東京,大阪,福岡,札幌での学術大会の開催,学会誌の発行,タイムリーな企画セミナーや他学会との共催シンポジウムの開催などの事業を行ってまいりました.
現在,会員数は550名,賛助会員41社になり,皆さん方の絶大なるご支援によりまして極めて順調に推移してまいりました.創立当初,歯科用CAD/CAMテクノロジーはまだまだ認知度が低く,海外に比較しても普及率も十分ではありませんでした.しかし,最近では,新素材としてジルコニアの開発,CAD/CAM冠の医療保険導入などによって画期的な飛躍があるとともに,3DパノラマやCTなどの画像診断,歯冠修復だけでなく矯正治療への応用,患者カルテやレセプトのオンライン化など,歯科診療にデジタル化の波が大きく寄せてまいりました.そこで3年前には「日本デジタル歯科学会」と改称し,幅広く学際的研究の成果を発表できるように努めてまいりました.
今般,さらに歯科におけるデジタル化の普及に伴って,多様な材料開発,CAMの進展,患者の高度な要求とともにデジタル機器の活用に対する社会的な責任が問われる時代になってまいりました.そこで,昨年より理事会,総会において「法人化」について検討し,関係各位のご尽力も賜って,平成28年4月1日より「一般社団法人日本デジタル歯科学会」として新しく生まれ変わりました.
今後は,歯科医療に関わる多くのデジタル機器や材料の開発,研鑽,啓蒙などを活発に行い,国民に最新機器を用いて安全,安心,信頼できる歯科医療の提供を目指したいと考えています.会員の皆様におかれましては,なお一層のご理解と温かいご支援,ご協力を賜りますようお願い申し上げます.
平成28年4月1日
一般社団法人日本デジタル歯科学会
理事長 末瀬 一彦(大阪歯科大学)
学会誌 Vol.5 No.1 April 2015
《巻頭言》デジタルデンティストリーの社会貢献
平成26年4月,歯科用CAD/CAMシステムを用いたハイブリッドレジン冠が新規に保険導入され,歯科医療の治療と技術にイノベーションを巻き起こしている.これまでの金属を用いた歯科精密鋳造やコンポジットレジンを用いた光・加熱重合から,ハイブリッドレジンブロックを用いた切削加工で審美性に優れた修復装置を作製し,歯科用接着材により歯質と複合化して,口腔内で長期間機能している.
この歯科治療に患者は自分の歯で一生の間しっかり咬合する,食物を咀嚼・嚥下する,美しい歯で楽しく会話するなど人生のQOL(生活の質の向上)に強い関心を寄せている.歯は,スマイルラインに調和した歯並び,色調を有している.ところが長期間機能している口腔内の顎骨や歯は,咬み合わせ,う蝕,歯周病,外傷などにより損傷を受け,エナメル質の咬耗や歯の欠損を生じる.そこで、歯科における補綴治療は,硬組織である歯質(エナメル質,象牙質)を外科処置(切削)し,バイオマテリアル(生体材料)で作製した人工臓器(歯冠補綴装置)を装着し,健康の維持増進と管理をはかっている.その補綴治療では,バイオマテリアルを用いた補綴装置に審美性と機能性および生体適合性に対する要求を増大させている.このようなバイオマテリアルには,金属,セラミックス,コンポジットレジンなどが単体または複合体として応用される.
最近のデジタルデンティストリーにおける歯科用CAD/CAMは,単に補綴装置を作成する機器というクローズドシステムから,多くの工程をデジタルデータで構成できるオープンシステムネットワークとして位置付けられている.オープンシステムを採用して,口腔内スキャナーによる支台歯の形状測定や作業模型の形状測定による3DCADデータ(STLデータ)から,補綴装置の最適形状をインターネットからCAD伝達情報に取得できる.そしてデータを基に,いかなるCAM機を使っても高い精度をもって審美補綴装置が作成できる.MIにおける接着治療では,自己治癒可能なエナメル質は可及的に切削しない.切削したエナメル質や象牙質は接着材で接着処理し,耐酸性を高めて辺縁漏洩を防止し,その結果2次齲蝕の予防が可能になり,歯の保護ができる.バイオマテリアル研究に基づく基礎データと臨床評価による審美補綴治療で,日本デジタル歯科学会はさらなる国民医療への貢献が期待されている.
日本歯科大学
名誉教授 新谷明喜
学会誌 Vol.4 No.1 April 2014
《巻頭言》デジタル・デンティストリーの急速な進化
我々が考えうる範囲をはるかに超える速さで補綴におけるデジタル化は進んでいる。この事を裏返して見ると、補綴治療はこの分野のみしか発展の余地がないと言う事かも知れない。
いずれにしても、CAD/CAMの精度とマテリアルの充実は素晴らしいものがあり、十分、我々補綴医を満足させるものになりつつある。ソフトウェアの開発にゴールというものは無く、無限の可能性を秘めている。各社はこの一点にしのぎを削っていると言っても過言ではない。様々なCAD/CAMシステムの中で、セレックのエステティック・デジタルアナライズ等は審美治療を完全にデジタル化し、歯・口唇・顔貌と調和した修復物のデザインを3次元的に決定する事を可能にしている。これらの技術により、将来的に進化していくであろうし、又より実用化が臨床的に筒便性を持ち合わせていき、汎用性が高まる事が予測される。一方マテリアルの開発も様々な種類において進化しており、例えは顔貌、口腔内の写真と模型から審美分析及び修復物デザインの決定、プロビジョナル・レストレーション、最終補綴物まで全てデジタル・ソリューションが可能になり、それに合わせたレジンからセラミックまで様々なマテリアルが選択可能となる。
長い間CAD/CAMを用いて臨床を行ってきたが、現時点においてCAMの精度はそれ程各社に有意な差はないと感じている。一方、CADの汎用性にはかなりの違いがあると思っている。即ち前述した通り、ソフトウェアの新たな開発がそのまま利便性となり、大きな差となって現れている。又、臨床上使い勝手が良く筒便性が高い事も重要である。しかしながら、補綴治療においてCAD/CAMは必須のアイテムとなっている事に間違いはない。また、これを使用する事により技工自体の枠組みが大きく変化しつつある。
今後、より一層使用頻度は増し、補綴治療は変化し続けるであろう。
日本デジタル歯科学会
副会長 山﨑長郎
学会誌 Vol.3 No.1 April 2013
《巻頭言》CAD/CAMシステムの進化と本学会の役割
日本歯科CAD/CAM 学会会員の皆様、平素は学会運営に対しまして絶大なご支援を賜り、誠にありがとうございます。学会が発足して4年目になりますが、会員数も徐々に増加し、350 名を数える状況です。企業各社にもご協力をお願いして30 社を超えています。平成25 年4 月20 日、21日には昭和大学歯学部におきまして、前会長の宮崎隆先生のもとで「第4 回CAD/CAM 学会学術大会」が開催されます。補綴・技工に限らず、CT や矯正治療、診査診断など本学会の目的でもありますデジタルデンティストリーの発展を目指した幅広い内容の学会が開催されます。会員だけでなく、多くの歯科関係者にご参加いただきたいと存じます。
さて、今年はIDS 開催の年で、3 月13 日から16 日までドイツのケルンで第35 回大会が盛大に開催されました。4 日間の来場者が49 カ国から125、000 人と2 年前に比べて6%増加し、出展企業も56 カ国から2、058 社になっています。とりわけ興味深かったのがやはりCAD/CAM システムとデジタルワークフローテクノロジーでした。2 年前のIDS ではとにかくCAD/CAM システムのオンパレードでCAM システムにいたっては歯科とは無縁の工業界からのミリングマシーンの出展が目につきましたが、2 年経た今回のIDSではスキャナー・CAD 及びCAM システムはかなり絞られて淘汰されてきた感があります。口腔内スキャナーもコンパクトになり、パウダーレスによって画像もクリアで、シェードマッチングさえ可能なところまで進化しているようです。また、CAM においても小・中規模の歯科技工所に設置できるような小型のタイプと半ばロボット化された大型のミリングマシーンや積層装置に2 分されてきたようです。また、従来型の歯科診療所内での完結型(スキャナー・CAD・CAM の一体型)と、スキャナーとCAD・CAM を完全に分離することによって、スキャナーのコストダウンをはかり、データ送信によって歯科技工所とのコネクトをするシステムが注目されていました。さらに、マテリアルも豊富で、特にジルコニアは高強度タイプあるいは高透光性タイプ、グラデーションタイプなどが開発され、ますます審美性の高い修復物の製作が可能となってきています。このように、CAD/CAM システムはもはや特別な装置ではなく、補綴診療におけるツールとして一般化されつつあります。
私たちのCAD/CAM 学会におきましても、できるだけ最新情報を発信することによってデジタルデンティストリーの啓蒙をはかり、さらには基礎的・臨床的な研究を発表し、更なる進化に向けて討論していきたい所存です。まさに、研究者、臨床家、開発企業が一体となって、同じ土俵の上で研鑽したいと思います。また、学生教育面においても大学や専門学校での講義実習に組み込まれるような教育カリキュラム内容を構築させることも責務であります。国際的にもデジタルデンティストリーに関する学会や研究会が徐々に設立されるなかにあって、本学会も会員諸兄のお力添えで、日本を代表する専門分野の学会として大きく発展していきたいものです。今後ともよろしくご指導賜りますようお願い申し上げます。
日本歯科CAD/CAM 学会
学会長 末瀬一彦
学会誌 Vol.2 No.2 January 2013
《原著》CEREC システムにおける光学的咬合採得による咬合関係の再現性
岩城有希,若林則幸,五十嵐順正
本研究は光学的咬合採得で再現した咬合関係の精度の評価を目的とした.模型上に測定点を設置し、三次元測定器で対合同名歯との測定点間距離、上下顎平面の水平的・垂直的角度を測定し、基準値とした.単一歯及び複数歯修復を想定し、それぞれ光学的及び物理的咬合採得で咬合関係を再現した後、基準値との差を測定した。
一元配置の分散分析後、Tukey の多重比較検定を行った(α=0.05)。単一歯において光学的咬合採得の水平的角度の差は物理的咬合採得より小さく、修復部である臼歯の測定点間距離の差に物理的咬合採得との有意差はなかった(p>0.05)。複数歯修復では測定項目の多くで基準値との差が有意に大きかった(p<0.05)。
現在のシステムにおける光学的咬合採得は単一歯修復に最も適していることが示唆された。
学会誌 Vol.2 No.1 April 2012
《総説》歯科用CAD/CAMシステムの現状
蛯原 善則
近年、歯科補綴物の作成において歯科用CAD/CAMシステムを利用することが定着してきており、欧米諸国、日本国内においても既にCAD/CAM市場は確立されたといえる。高精度品質と生産性の維持だけではなく、ハンドワークでは作成が困難なチタンやジルコニアなどの材料、インプラント上部構造などの補綴物までの適用もなされ、今や歯科用CAD/CAMシステムを利用した技工は標準になりつつある。作製できる補綴物の種類も年々増加しており、歯科用CAD/CAMシステムの応用範囲は急速に広がっている。さらに、歯科用CAD/CAMシステムは補綴物を作成する装置という時代から、デジタルデータを活用するネットワーク内の一つのシステムとして位置づけられ始めている。
このような背景から歯科で導入されているさまざまな計測方法や加工技術、歯科用に特化しているCAD/CAMソフトウェアの機能紹介だけではなく、フルシステム導入と加工を利用する運用方式の違いや、最近話題となっているクローズドシステムとオープンシステムなどについても触れながら、歯科用CAD/CAMシステムの現状について紹介する。
学会誌 Vol.1 No.1 April 2011
発刊に寄せて
20.03.2011
第2回日本歯科CAD/CAM学会学術大会
大会長 新谷明喜
日本歯科CAD/CAM学会誌(The Journal of Japan Academy of CAD/CAM Dentistry)Vol.1 No.1 April 2011を発刊いたしました。総説には、会長の宮崎 隆先生に”Digital Dentistryの現状と将来展望”の執筆をお願いしました。しかいりょうの高度化に対応して、患者さんとのコミュニケーション、検査、診断、治療計画(シミュレーション)、手術支援、患者管理などを含めたこれらのデジタル技術の応用が進められる。さらに審美修復の臨床では、実際にCAD/CAMによる修復装置が制作され、歯科技工士と歯科医師の新たな技術として脚光をあびている。このようなCAD/CAMを含めたDigital Dentistryがこれからの歯科医療の発展に貢献します。
第2回日本歯科CAD/CAM学会学術大会を2011年4月2日~3日の両日、日本歯科大学生命歯学部(東京)の富士見ホールで開催させて頂きます。本大会では、メインテーマにCAD/CAM医療イノベーションを掲げました。第1日には、大会長講演としてCAD/CAMによる補綴治療イノベーション、臨床講演としてコンピュータ支援による診査・診断および治療、シンポジウム1としてデジタル審美歯科のイノベーションです。第2日には、シンポジウム2としてCAD/CAM技工の最前線、特別講演としてコンピュータ支援による歯科医学教育への提言、トピックスとしてIDS海外CAD/CAM最新情報、ランチョンセミナー、企業講演、最後にシンポジウム3としてセラミッククラウン・ブリッジの技工と臨床を企画しました。さらにポスター発表20演題および企業展示22社と本大会への大きな期待が伺われます。
本大会では、展示担当者さんを含めたその企業で働く社員や研究者にご参加頂き、歯科臨床にご理解いただくと共に、学部学生、歯科技工士、臨床医、研究者、企業皆様との楽しいコミュニケイションの場としました。これからも、皆様のご支援、ご援助をよろしくお願いいたします。